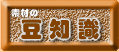
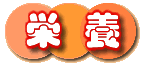
□■□食物繊維編□■□
食物繊維というと、「便秘の解消」というイメージがありますが、食物繊維とはいったい何でしょう?
食物繊維の定義は時代と共に変わってきましたが、現在は「人間の消化酵素によって消化されない、食品中の高分子の難消化性成分の総体」とみなされています。
食物繊維は、植物性食品、動物性食品に含まれ、食品によって種類も様々あります。大きく分けて、「水溶性」のものと、「水不溶性」のものの2種類に大別されます。水溶性のものと、水不溶性のものとでは、理化学的性質にかなりの違いがある為、生理作用も大きく異なります。
植物性食品の中に含まれる繊維類は、植物細胞を構成する成分で、栄養学的には「炭水化物」に属します。しかし、繊維類を消化する酵素が消化液中に存在しない為、エネルギー源として利用される事はありません。また、動物性食品の難消化性多糖類や、人工的に合成された多糖類の中にも、同じように消化されないものが有ります。
炭水化物の中の食物繊維は、下記の表の様になります。
|
炭
水
化
物
|
糖質
|
単
糖
|
ぶどう糖 |
|
|
利用可能
炭水化物
|
|
| 果糖 |
|
|
|
|
二
糖
|
しょ糖 |
|
|
|
| 乳糖 |
|
|
|
| 麦芽糖 |
|
|
|
|
多
糖
|
デキストリン |
|
|
|
| でんぷん |
|
|
|
| ガム |
水溶性食物繊維
|
|
利用不能
炭水化物
|
食
物
繊
維
|
| 粘質物 |
水溶性食物繊維 |
|
| 海藻多糖類 |
水溶性食物繊維 |
不溶性食物繊維 |
| ペクチン質 |
水溶性食物繊維 |
不溶性食物繊維 |
|
繊維
|
ヘミセルロース |
|
不溶性食物繊維 |
| セルロース |
|
不溶性食物繊維 |
そ
の
他
|
リグニン |
|
不溶性食物繊維 |
非炭水化物
|
甲殻類の
構造物質 |
キチン |
|
不溶性食物繊維 |
食物繊維の持つ主な生理作用は次の6つあります。
1.保水性があり、膨潤して排便を促進する。
2.コレステロールや胆汁酸などを吸着し、排泄する。
3.腸内細菌を繁殖し、糞便量を増やす。
4.腸内の善玉菌を増やす。
5.少量の食物で満腹感をもたらす。
6.血糖の上昇を遅らせて、糖尿病を予防する。
これらを、以下に説明致します。
1.保水性があり、膨潤して排便を促進する。
食物繊維は消化されない上、吸水、保水する能力を持っています。(抱水能)。一般に、「水溶性食物繊維」は、水との親和性が強く、共通して※1.ゾルや※2.ゲルを形成します。小腸は、スポンジの様に膨れ上がった食物繊維やゲルになった食物繊維などを不要なものとして、先へ先へと送っていきます。更に先の大腸でも同じで、糞便の溜まり易い下行結腸から直腸の部分もすんなり通過します。その為、腸内の停留時間が短くなり、排便が促進される訳です。
ペクチン質の含有量の多いりんごやにんじんに含まれる繊維は、それ自身の約30倍もの水分を保持します。りんごが便秘解消に良いとされる理由ですね。
2.コレステロールや胆汁酸などを吸着し、排泄する。
腸内には、食品に含まれるコレステロール以外にも、胆汁に含まれているコレステロールも大量に存在しています。これらのコレステロールはそのまま排泄されれば問題無いのですが、腸管から吸収されると、血液中コレステロールが増加し、動脈硬化の原因にもなってしまいます。食物繊維はこのコレステロールを吸着する働きを持っていますのでコレステロール禍を防ぎます。
動物性脂肪をたくさん摂取すると、食品だけで無く、その消化に必要な胆汁酸の分泌量も増えます。この胆汁酸は、腸内細菌などの作用によって、発ガン作用のある成分に変化します。食物繊維は、これらの発ガン物質を吸着し排泄しますので、危険性が低くなります。
3.腸内細菌を繁殖し、糞便量を増やす。
人間の腸内(主に大腸)には、約100種類の腸内細菌が繁殖、共生しています。これらの腸内細菌は、食物繊維などの消化吸収されないものを分解し、餌としています。水溶性のペクチン質、植物ガム、粘質物などは、ほぼ完全に分解されます。水不溶性のセルロースはわずかに分解されるだけで、リグニンはほとんど分解されません。
腸内細菌は、ビタミンB1、B2、ナイアシン、葉酸、ビタミンKなどを合成し、人体へ供給しています。また、外部から浸入する腐敗菌や化膿菌などの撲滅に役立ったり、免疫の仕組みを強くするのに役立っています。
4.腸内の善玉菌を増やす。
健康な状態の糞便に含まれる水分量は、排出量に左右される事無く約75%と一定です。糞便の重量のうち約40〜50%は、腸内細菌に由来するものと言われています。(その他は、食物繊維などの食べ物の残りかすや、消化液の成分、胃腸壁のはげ落ちたものです。)
つまり、食物繊維をたくさん食べると糞便の量が増えるのは、消化されない食物繊維だけでなく、腸内細菌とその死骸の増加によるものと言えます。
肉を食べた時に臭い糞便やガスが出るのは、蛋白質が、腐敗菌などの作用で分解(腐敗)した為です。しかし、食物繊維を餌として繁殖する善玉菌の場合は、糞便もガスも臭くないのが特徴です。
その点から、食物繊維をしっかり採る事で善玉菌を増やし、悪玉菌を少なくする事は重要な事と言えます。
5.少量の食物で満腹感をもたらす。
食物繊維を多く含んだ食べ物は、胃内の停滞時間が長くなります。その為満腹感をもたらします。また、食物繊維は水分を多く含んでいますので、量は多くてもエネルギー源にはほとんどなりません。一部が食物繊維を餌としている細菌によって発酵させられ、その時に発する熱エネルギーになる位ですので、ダイエット向きと言えるでしょう。
6.血糖の上昇を遅らせて、糖尿病を予防する。
糖尿病は、インスリンの不足によっておこります。その原因として、長期にわたるインスリンの分泌が挙げられます。
食物繊維が多い食事は、胃内での停滞時間が長くなる為、小腸における消化吸収を遅らせる事になります。その結果、でんぷんの消化産物であるブドウ糖の血糖増加速度が遅く、緩やかになり、血糖の上昇を抑える働きを持つインスリンの分泌が少なく済みます。
では、食物繊維の採り過ぎが人体に与える影響を考えてみましょう。
食物繊維を多く含んだ自然食品を食べると、糞便の量は多くなります。この場合、食べる量に比例した量の各種ミネラルを採っているわけですので、排泄量が増えても問題はありません。
しかし、食物繊維を異常に摂取した場合、下痢をする事があります。これが問題で、食品に含まれているミネラル分が、多量に排泄される水分と一緒に排泄されてしまいます。食品に含まれる分だけでなく、消化液に含まれ、血液から分泌された分のミネラルも失われてしまいます。
最近の自然食品でない「食物繊維飲料」の場合は、摂取するミネラルの量が増えるわけではないので、特に、下痢症によるミネラル不足には注意しましょう。
では、1日の食物繊維の摂取量はどの位が望ましいのでしょうか?
一般には20〜25g位が目安とされているようです。
[1日の推奨摂取量(1種類の食品で見た場合)]
| 寒天 | 25g | りんご(大) | 8〜9個 |
| 干瓢 | 70g | 干し椎茸 | 50g |
| ゆで大豆 | 300g | 切干大根 | 100g |
| 食パン | 20枚 | 納豆 | 300g |
Back to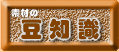 Page.
Page.
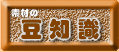 Page.
Page.
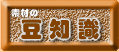
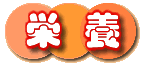
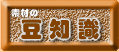 Page.
Page.